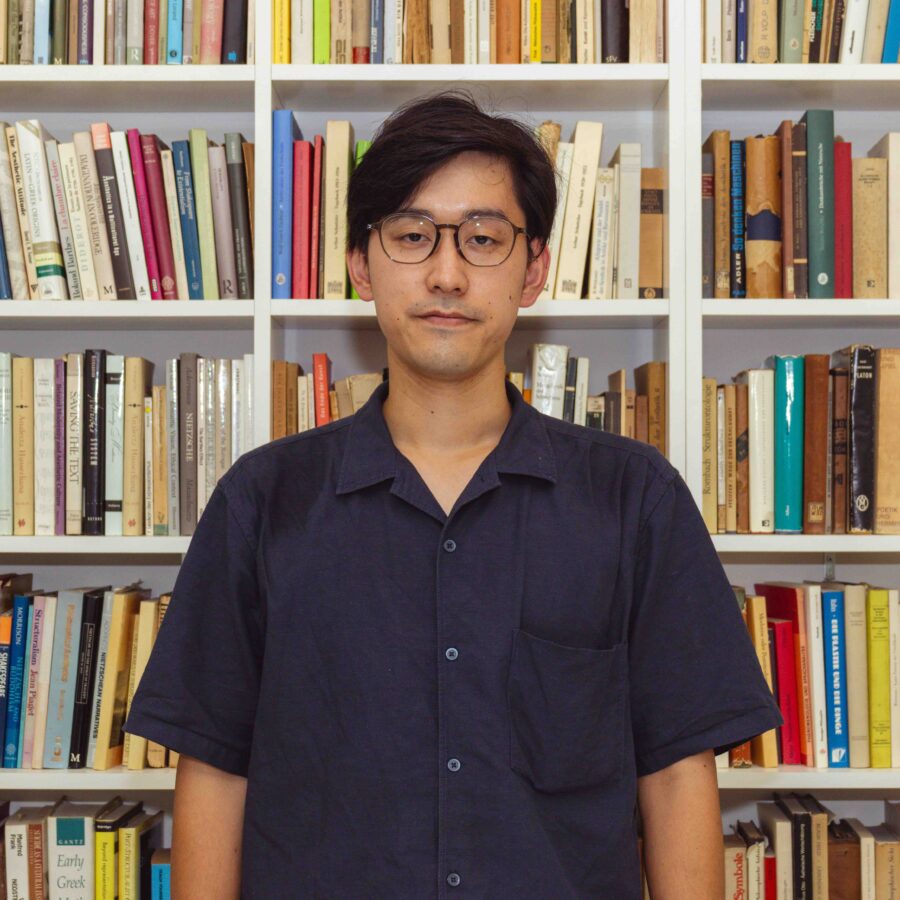
菅原海人さん
編集者、ライター
とにかく具体的に。芸術学科で学んだ執筆のワザ
雑誌やWeb媒体の編集・執筆を手がけるフリーの編集者、ライターである菅原海人さん。
東京と静岡での出版社勤務を経て、現在は地元熊本を拠点に活動中だ。
16年の熊本地震を機に「地元に貢献したい」との思いを強め、地域の魅力を発信する仕事にも取り組んでいる。
大学時代の学びと現在の仕事について聞いた。
菅原海人さんが熊本市・内坪井にある文豪夏目漱石の旧居を取材し、同市が発行しているウェブマガジン『くまもとジャーニージャーナル!』に記事を載せたのは、2023年のことだった。漱石が熊本に住んでいたのは、1896年から4年間。まだ小説を書き始める前の時期で、英語教師として第五高等学校(現・熊本大学)で教鞭を執っていた。記事によると、旧居の見どころは二つ。漱石が詠んだ俳句が書かれた掛け軸が飾られた床の間と、縁側に面して文机が置かれている書斎だ。漱石は生涯に2000以上の句を残した俳人の顔を持つ。熊本でも、熱心に多くの句を詠んでいた。旧居には瀟洒な庭があり、漱石が過ごした空気がよくわかる。取材中にたまたま近所の猫が訪ねてきたことも、写真で紹介されている。さすが、漱石の旧居だなと思わせる記事になっている。
現在、フリーランスの編集者・ライターとして、熊本市で活動している菅原さんの仕事は、雑誌などの紙媒体や電子媒体の企画立案から取材、執筆、編集、校正と多岐にわたる。以前の出版社在籍時には、編集者としてある官庁の広報誌の制作に携わった。業務は年間のテーマを企画出しするところから始まり、各号の具体的な特集構成や取材先の選定、各号の特集案とラフを作成し、先方に提案する。会議により企画を決定した後、デザイナーや表紙イラストレーターと打ち合わせをし、方向性をすり合わせる。そして、取材アポイント・日程調整を行い、取材。原稿や写真といった素材の整理と修正、デザイナーから上がってきたゲラの確認と初校の作成、関係各所への確認の末、校了・入稿となる。菅原さんはこの全ての仕事を担っていたのだ。2022年発行号では、当時のトレンドだった「メタバース」をテーマに、XR領域で先進的な取り組みをしていた企業の取材や、仮想空間での知的財産の扱いについて弁護士取材の成果が記事になった。
菅原さんが編集・ライターとして最も大切にしているのは、現場で得た感覚をどのようにして読者に伝えるかという点だ。例えば飲食店を取材する際には、料理の味や香りだけでなく、店主の立ち居振る舞いや客とのやり取りまで観察し、記事に落とし込む。
菅原さんが取材やライターの世界に足を踏み入れたのは、多摩美術大学在学中の経験が大きかった。芸術学科の小川敦生教授のゼミで行ったフィールドワークや卒論制作を通じ、「取材して記事を書くことの面白さ」を実感したという。2015年に卒業し、東京・神田神保町の大空出版に入社。編集者兼ライターとして多様な媒体に携わった。
同社では月刊のフリーペーパー『ホットペッパー』のご当地特集記事の編集を約4年担当した。各地の制作チームが集めた企画・取材をまとめ上げ、スケジュール管理やデザイン・原稿のクオリティ管理を行う取りまとめ役として、編集プロダクションやデザイナーとの橋渡しも務めた。
22年、静岡支局勤務を経て退職。出身地の熊本に戻り、フリーランスとして活動を始めた。決断の背景には、16年の熊本地震があった。東京でニュースを見ていることしかできなかった無力感から、「地元に貢献できる仕事をしたい」という思いが芽生えたと語る。現在は熊本を拠点に観光サイトや移住情報サイトの記事などを手がける一方、首都圏の企業のオウンドメディア(企業等が自ら制作する媒体)など、多様な媒体を担当している。
これまでで特に印象に残っている仕事は、入社間もない冬から翌年春まで携わった、日本の工芸品などの地場産業品を紹介する書籍の制作だという。全国各地の工芸品や職人の仕事を取材し、一冊にまとめるという大規模なプロジェクトだった。そこで菅原さんは、担当した職人から「文章が思いを正しく伝えていない」と厳しく叱責された。完成した原稿を作家に何度も見せ、表現の調整を重ねてもなお、思いが十分に文章に映し出されていないと指摘されたのだ。工芸品が持つ唯一無二の質感や職人の妥協のないこだわりを、安易な言い換えや簡単な言葉で表現したことが、作家にとっては受け入れがたいものだった。それを痛感したことは菅原さんにとっても大きなショックだったが、適切な表現を模索しながら作家の声を最大限に反映させた経験は、菅原さんの取材姿勢を形づくる大きな契機となった。
大学時代の学びも今に生きている。海老塚耕一教授の「まなざし」に関する講義では、「見る」という行為を単なる視覚にとどめず、音や匂い、触感など五感を通じて対象を全身で受け止める姿勢を学んだ。「見る」ということの複雑さや多様さを認識することは、取材先での観察や記事執筆に直結する視点だという。
また、本江邦夫教授から学んだ「Zeitgeist(時代精神)」という概念も重要な指針になった。たとえば伝統工芸や祭りを扱うときでも、「今を生きる私たちにとってどんな意味があるのか」を常に問い直す。菅原さんは「表現者は時代精神を忘れてはならない」という言葉を胸に、読者に届く言葉を模索してきた。
さらに、小川教授のゼミでは、「言葉にならない感動を言葉にすること」の難しさに直面した。作品や作家の持つ熱量をどのように具体的な文章に変換するか。小川教授が繰り返し強調した「とにかく具体的に」という姿勢は、今も取材や執筆の現場で大きな支えになっている。
菅原さん取材風景
熊本市観光情報サイト「くまもとジャーニージャーナル!」・熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?」の記事
取材・文=川田宗志郎
撮影=市川虎ノ助
プロフィール
菅原海人(すがはら・かいと)
2015年多摩美術大学芸術学科卒業。大空出版にて編集者・ライターとして勤務後、2022年よりフリーランスになる。熊本市を拠点に、観光や自治体広報、企業広報など幅広い記事制作に携わる。


